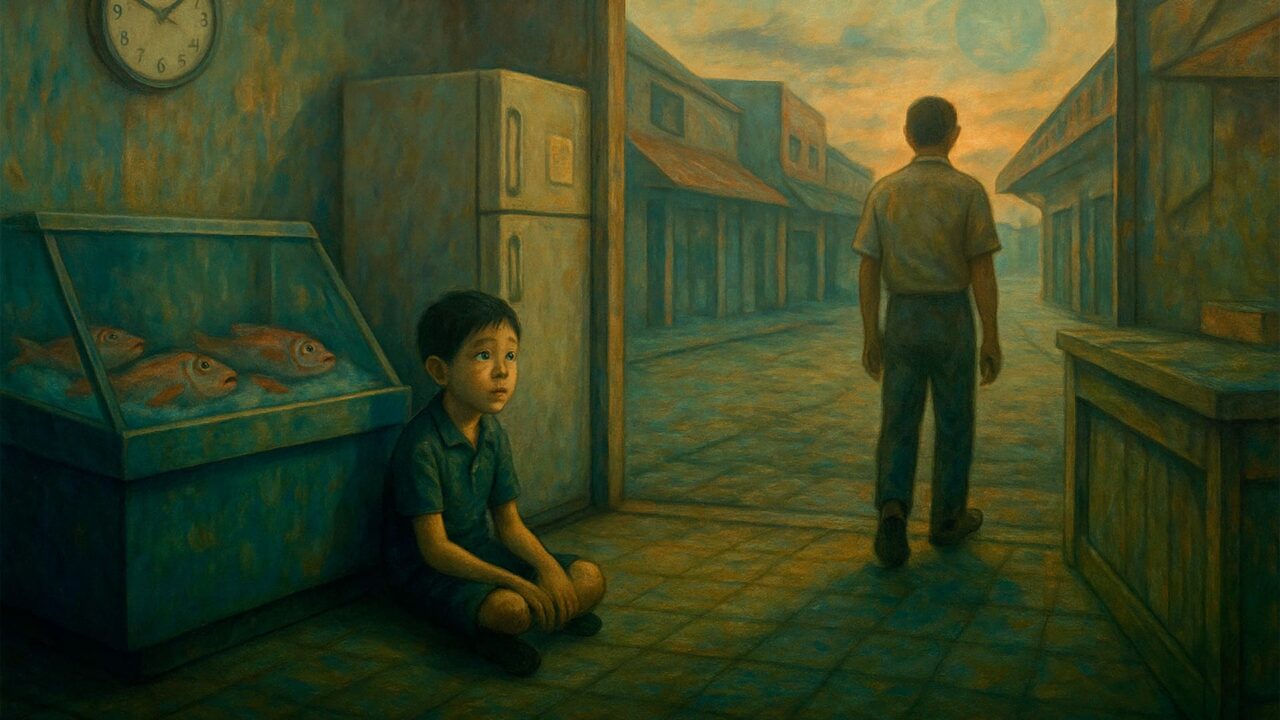
それは、私が8歳の頃に体験した、今も忘れられない出来事です。
我が家は商店街の一角にある魚屋で、年中無休で営業していました。
ある日、目を覚ますと、家の中には誰もいませんでした。
店は閉まっておらず、いつも通り営業しているはずなのに、本当に誰もいなかったのです。
※
私は「お客さんが来たら大変だ」と思い、一人で店番をすることにしました。
ところがすぐに、ある“異変”に気がつきました。
時計を見ると、朝の9時頃でした。
けれども、店の奥の入り口から外の景色を見ると、そこにあるべき“朝の明るさ”が感じられなかったのです。
空はまるで夕方のようにグレーがかっており、太陽は出ているのに、あのオレンジ色の光が一切ありませんでした。
それは、ただただ冷たく光のない“灰色の夕陽”でした。
※
私は店の前でしばらくぼんやりしていました。
10分ほど経った頃、ふと気づきました。
――誰一人として通行人が現れないのです。
それだけではありません。
商店街のはずなのに、物音が一切しないのです。
風の音も、車の音も、人の気配も……なにもかもが、まるで“消されている”かのように静まり返っていました。
私は急に怖くなって、家のリビングへ戻り、冷蔵庫にもたれ掛かって座り込んでしまいました。
※
あまりの静けさが不気味で、テレビをつけることにしました。
しかし、どのチャンネルに変えても画面は砂嵐のまま。
「ザーッ」というノイズ音すら聞こえないのです。
――これはもう、幽霊が近くにいるに違いない。
ビビリだった私は、そんな直感に突き動かされて、すぐに家を飛び出しました。
けれども、商店街にはやはり誰もいない。
すべての店は開いているのに、声も音も気配もない、異様な空間でした。
※
しばらく彷徨っていると、やがてひとりのおじさんが立っているのが見えました。
思わず駆け寄り、シャツを掴んで泣きつきました。
そのおじさんは私を見下ろしながら、少し戸惑ったように言いました。
「なんで君、ここにいるんだ? 他の人には誰にも会ってないか?」
私は状況がわからず、ただ首を横に振るばかりでした。
「ここは本来、俺の地域じゃないんだけどな……」
おじさんは明らかに困った様子でした。
そして、ひとつ息をつくとこう言いました。
「仕方ない。おじさんが助けてあげる。目を閉じて、三つ数えて」
※
私は言われるがまま、目を閉じて「いち、に……」と数え始めました。
そのとき、急に軽い頭痛に襲われました。
頭の中が少しだけ、ズンと重くなったような感じでした。
それでもなんとか落ち着いたので、三つ目を数える前に、つい目を少しだけ開けてしまいました。
すると、そこは――
完全な闇でした。
本当に、何も見えないほどの真っ暗闇だったのです。
掴んでいたはずのおじさんのシャツも、そこにはありませんでした。
※
そして次の瞬間――
私は、自宅のリビングの冷蔵庫の前に座り込んでいました。
気がつくと、母がそこに立っていました。
「……あれ? さっきまであんた、二階にいたよね? いつ降りてきたの?」
そう問いかける母に、私は何も答えることができませんでした。
ただ、ようやく“元の場所”に戻ってこられたという安堵だけが、胸の奥で静かに脈打っていました。
※
あの時、私はどこにいたのでしょうか。
商店街は確かに“そこにあった”のに、人も音も時間も、どこかずれていた。
そして、「ここは俺の地域じゃない」と言ったあのおじさん。
彼が何者だったのか、なぜ私を“助ける”ことができたのか。
今でも答えは見つかりません。
ただ、あの朝だけは――私が知っている現実とは、少し違っていたのです。
















