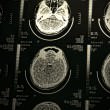「これまで、いろんな霊体験をしてきたって言ってたけど、命の危険を感じるような、洒落にならないくらい怖い体験って、ある?」
ある日、ふとした会話の流れで、以前付き合っていた“霊感の強い女性”にそう尋ねたことがある。
彼女は少し黙ってから、静かに、しかし深刻な面持ちで語り出した。
「……あれは、19年前のこと」
※
当時、彼女は家電量販店で働いていた。
ある日、注文されたテレビの配達業務で、K県内のある町へ向かうことになった。
その町には彼女の叔母が住んでおり、配達先を尋ねがてら、叔母の家に立ち寄った。
偶然にも目的地はすぐ近くだったため、手早く配達を終えた。
※
帰り道、彼女は時間短縮のため、Nダム沿いの裏道を通ってK市へ戻ることにした。
その日は曇天で、時折、霧のようなものが視界を遮っていた。
走るにつれ、舗装された道路はいつの間にか細い山道に変わり、木々に囲まれた不気味な雰囲気が漂い始めた。
道に迷い始めた頃、道端で農作業をしている年配の女性を見つけた。
「K市へ行きたいんですが、この道で合ってますか?」
そう尋ねると、お婆さんは道の奥を指し、「この先に民家があるから、そこで聞いていくといいよ」と言った。
※
彼女はその言葉に従い、車をさらに進めていった。
すると、木々の間からポツンと一軒家が姿を現した。
玄関に車を停めようとしたその瞬間、まるで待ち構えていたように、あのお婆さんが再び姿を現した。
「まぁまぁ、せっかくだから、お茶でも飲んでいきなさい」
彼女は断ろうとしたが、どこか誘われるような不思議な感覚に抗えず、つい足を踏み入れてしまった。
※
家の中は、どこか古くて重たい空気が漂っていた。
居間には、背筋の伸びた白髪の老人が静かに座っていた。
その男は彼女の顔を見るなり、まるで旧知の人に会ったかのように、こう言った。
「……きょうこさん、よく戻ってきたねぇ」
彼女は困惑した。
「きょうこ」などという名前で呼ばれたことは一度もない。
そのとき、なぜか納屋の方から微かな気配を感じた。
そして、いつの間にか縁側に座らされていた彼女の意識は、ふっと途切れた。
※
目を覚ますと、彼女は仏間に寝かされていた。
視界の端に、小さな影があった。
――幼い女の子が、彼女の腕を握っていたのだ。
その子は何も言わず、突然お爺さんに向かって駆け寄り、鋭い牙で腕に噛みついた。
お爺さんは無言で受け止めていたが、目はどこか虚ろで、生きているようには見えなかった。
彼女は恐怖のあまり逃げようとしたが、体が動かない。
見ると、畳の隙間から無数の手が伸びてきて、彼女の身体をがんじがらめにしていた。
「助けて……!」
叫ぼうとしても声が出ない。
意識が遠のきかけたそのとき――
お爺さんの姿が、まるで崩れるように“異形”に変わっていった。
口が裂け、瞳は黒く染まり、そして……彼女の耳元でこう囁いた。
「“きょうこ”は……倉にいる。あんたは“妹”だ」
※
次に目を覚ましたとき、彼女は外に立っていた。
空はどんよりと曇り、足元はぬかるんでいた。
背後から足音が近づく。
振り返ると、あのお婆さんが無表情で立っていた。
「行っちゃ駄目だよ、きょうこさん……帰ってくるべき人は、あなたじゃない」
恐怖のあまり、彼女は車に飛び乗った。
キーを回す。エンジンがかからない。
何度も何度も試すうちに、ようやくエンジンが唸りをあげ、車は走り出した。
バックミラーには、お婆さんが何かを叫びながら、追ってくる姿が映っていた。
※
ようやく自宅にたどり着いた彼女は、安堵の中で異変に気づいた。
――財布の中から、免許証が消えていた。
翌日、警察署に問い合わせると、拾得物として届いているという。
彼女は引き取りに行き、免許証を手にした瞬間、全身が凍りついた。
写真が……自分ではなかったのだ。
見たこともない女性――しかし、どこかで見覚えのある気がした。
署員がふと漏らした。
「この名前、ダム近くで事故に遭った方と同じですね。“きょうこ”さん……2年前に亡くなってます」
※
彼女が経験したのは、単なる霊体験ではなかった。
現実と異界の境目が滲み、境界を越えて“名前”を呼ばれたことで、彼女の存在がすり替わりかけたのかもしれない。
日常のすぐ隣に、そういう“もうひとつの世界”が潜んでいる。
そんな恐ろしい真実を、彼女の話は静かに教えてくれた。