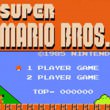ナーシャ・ジベリ――その名を聞くだけで、ゲーム開発者や熱心なファンは「天才」という言葉を思い浮かべる。
Apple II時代から「比類なきプログラマー」と呼ばれていた彼は、後に『ファイナルファンタジー』シリーズを根幹から支える存在となった。
※
『ファイナルファンタジーI』の開発中、デザイナーの石井浩一は坂口博信に「飛空艇に影をつけて、まるで空に浮いているように見せたい」と提案した。
しかし、当時のファミコンの性能を考えれば、それは到底不可能に思えた。坂口は「そんなの無理だ」と即答したという。
ところが、後日石井がナーシャに相談すると、翌日には影がついた飛空艇が実装されていた。しかも、ただ影があるだけでなく、飛空艇の移動速度は通常の4倍速に引き上げられていた。
開発チームは誰もが驚愕し、ナーシャの異次元の技術力をあらためて思い知らされることとなった。
※
その後『ファイナルファンタジーIII』のリメイク企画は、発表から実現までに実に6年もの歳月を要した。
理由のひとつとして、ナーシャが当時ファミコンの限界を超えたプログラムを書いていたため、後年のリメイクでは相応に高いハード性能が必要とされたことが挙げられている。
彼のコードは、当時の技術水準では「魔法」と呼ばれても不思議ではなかった。
※
伝説的なエピソードは枚挙にいとまがない。
ある時、『FFIII』の開発で重大なバグが発生した。スタッフが国外にいたナーシャへ電話で助けを求めると、彼は驚くべきことをやってのけた。
――バグを修正すべきプログラムコードを、その場で口頭で伝えたのだ。
田中弘道らがその通りに修正すると、嘘のようにバグは解消された。
坂口博信も同様の体験を語っている。ビザの都合で帰国していたナーシャに国際電話をかけ、症状を説明したところ、やはり彼は暗記していたプログラムリストを頼りに的確な指示を送り、問題は解決した。
ナーシャは、自分の書いたプログラムをすべて記憶していたのである。
※
彼が残した技術的特徴は数多い。
『FF』シリーズにおける飛空艇の高速スクロール、『とびだせ大作戦』での3Dスクロール、初期FFのスピーディな戦闘アニメーション、『聖剣伝説2』のリングコマンドなど、今では当たり前のように思える革新の数々は、彼の手によって生まれた。
さらに、遊び心にも満ちていた。
『ファイナルファンタジー』に隠された「15パズル」は、ナーシャが独自に組み込んだプログラムだった。
また『とびだせ大作戦』には、ディスクシステムのゲームとしては珍しいコピープロテクトが施されていた。コピーを検出すると “NASIR” の署名が入ったメッセージを表示し、起動できなくなる仕掛けである。
※
今振り返っても、ナーシャ・ジベリの存在は日本のゲーム史において異彩を放っている。
常識を超えた技術力、驚異的な記憶力、そして遊び心。
彼がいなければ、『ファイナルファンタジー』という世界的RPGの礎は存在しなかったかもしれない。
まさに「神業」と呼ぶにふさわしいプログラマーであった。
※
ナーシャ・ジベリは、ただ技術に秀でていただけではない。
彼の存在は、開発チームの精神的な支えでもあった。
※
ファミコンという限られたハードに挑むスタッフは、常に「これ以上は無理だ」という壁に突き当たっていた。
誰もが諦めそうになる瞬間に、ナーシャは涼しい顔で「やってみよう」と言い、翌日にはその壁を越えて見せるのだった。
たとえば、坂口博信が「そんなの不可能だ」と言い切った飛空艇の影。
それが翌日には、まるで最初から存在していたかのようにゲーム画面に表示された瞬間、開発室の空気は一変した。
「この人と一緒なら、どんな夢でも形にできる」
スタッフ全員がそう思わされたという。
※
彼の人柄は寡黙で、どちらかと言えば職人気質だった。
だが、不思議と周囲を安心させる空気を纏っていた。
緊張が走る会議の最中でも、ナーシャが一言つぶやけば、空気がふっと和らいだ。
彼の冗談は拙い日本語混じりで、それがまた仲間の笑いを誘い、重苦しいムードを消し去ってくれた。
※
また、開発チームの若手にとっても、ナーシャは憧れの存在だった。
彼の背中を追い、徹夜でコードを書き続ける者もいた。
田中弘道は後年こう語っている。
「ナーシャがいると、自分の限界を疑う気持ちが消えたんです。あの人はいつも『できるかできないかじゃない、やるかやらないかだ』と言ってくれていた」
※
そしてもう一つ、語り継がれる逸話がある。
ある日、デバッグで疲弊した若手スタッフに、ナーシャが突然「ちょっと待って」と告げた。
数分後、彼が差し出したのは、自分がプログラムに仕込んだ小さな「隠しゲーム」だった。
それは15パズル。
無機質な開発画面に突如現れた遊びに、疲れ切っていたスタッフたちは大笑いし、夢中になって遊んだという。
「仕事の中に、遊びを忘れるな」
それがナーシャの信条だった。
※
彼のプログラムは、時に「魔法」と呼ばれた。
だが本当の魔法は、彼が仲間に与えた希望と勇気だったのかもしれない。
坂口博信はこう回想している。
「ナーシャがいたから、僕たちは夢を形にできたんです。彼がいた時代は、奇跡のような時間でした」
※
ナーシャ・ジベリ。
その天才は、日本のゲーム史において、技術だけでなく「人の心に火を灯す力」を残した。
彼がいなければ、『ファイナルファンタジー』の物語は、今とは全く違ったものになっていたかもしれない。
※
ナーシャ・ジベリが日本を離れた後、開発室の空気は一変した。
彼が残したプログラムは、あまりに洗練されており、まるで「彼にしか理解できない言語」のようだった。
スタッフは必死に解析しようとしたが、コードはファミコンの限界をはるかに超え、時に「なぜ動いているのか分からない」とすら言われた。
※
その中で『FF III』の開発は進められた。
だが、重要なバグに直面したとき、皆が思った。
「ナーシャなら、きっとすぐに解決してくれるのに」
実際、ビザの都合で帰国していたナーシャに国際電話をかけ、症状を伝えると、彼は電話口でコードを暗唱してみせた。
驚くべきことに、その通り修正すると、バグはたちまち解消されたのだ。
彼はプログラム全体を、まるで頭の中に写し取るように暗記していた。
坂口博信は後に「まさに人間コンピュータだった」と語っている。
※
しかし、ナーシャ不在の影響は大きかった。
彼がいなくなって以降、後年『FF III』のリメイク版が発表されるたび、開発は難航した。
ファミコン版のプログラムがあまりにも特殊すぎて、解析と移植が想像以上に困難だったのだ。
2000年頃にリメイクの話が出てからも、企画は何度も仕切り直され、スタッフの間では「ナーシャの魔法を解ける者はいない」とすら囁かれた。
そして実際にリリースされたのは、最初の発表から実に6年後の2006年。
長い年月を経て、ようやく新しい形で『FF III』は世に送り出された。
※
だが、その裏には「もう一度、ナーシャに会いたい」という想いを抱き続けた開発者たちの苦悩があった。
田中弘道は、後年こう語っている。
「僕たちはずっと、ナーシャの残した謎に挑んでいた気がします。彼のコードは壁であり、同時に道しるべでした」
※
ナーシャ・ジベリという天才プログラマーは、日本のゲーム史に光を刻んだ。
彼が去った後も、その影響は深く残り続けた。
そして、『ファイナルファンタジー』という作品が「不可能を可能にする物語」であり続けられたのは、間違いなく彼の存在があったからである。
※
ナーシャ・ジベリの凄さは、技術力だけではなかった。
彼は、ゲームに「遊び心」を忍ばせることを忘れなかったのだ。
※
たとえば、初代『ファイナルファンタジー』には「15パズル」という隠しゲームが仕込まれている。
これはナーシャが、開発の合間に勝手にプログラムして入れ込んだものだった。
誰にも相談せず、密かに仕掛けた「いたずら」だったが、後にプレイヤーがそれを発見して大きな話題となった。
この“余白の遊び”は、FFシリーズに受け継がれる「隠し要素文化」の原点と言えるだろう。
※
また、彼の代表作『とびだせ大作戦』には、当時としては珍しいコピープロテクトが施されていた。
コピー版で起動すると、「NASIR」という署名入りのメッセージが表示され、ゲームを開始できない仕組みになっていたのだ。
これは、単なるセキュリティ以上に「自分の作品を守りたい」という強い想いが表れている。
そして同時に、それはひとつの“遊び”でもあった。
プレイヤーに対して「作り手の存在」を直接感じさせる、ユーモラスな仕掛けだったのである。
※
ナーシャは、技術の人でありながら、誰よりも「ゲームの楽しさ」を知っていた。
だからこそ彼のコードには、驚きと発見、そして笑顔が宿っていたのだろう。
※
彼が日本を去っても、彼の遊び心は作品に刻まれ続けた。
隠し要素を探すワクワク感。
不可能を超えるような演出の数々。
それはすべて、「ナーシャなら、もっと面白くできるはずだ」という精神の継承だった。
※
天才プログラマー、ナーシャ・ジベリ。
彼の名は、ゲームの歴史を語るとき、必ず現れる。
そして今もなお、彼の影響を受けた作品たちが、世界中で人々に冒険の楽しさを届けている。
技術と遊び心。
その両輪を持ち合わせた稀有な存在だからこそ、彼は“伝説”と呼ばれるのだ。