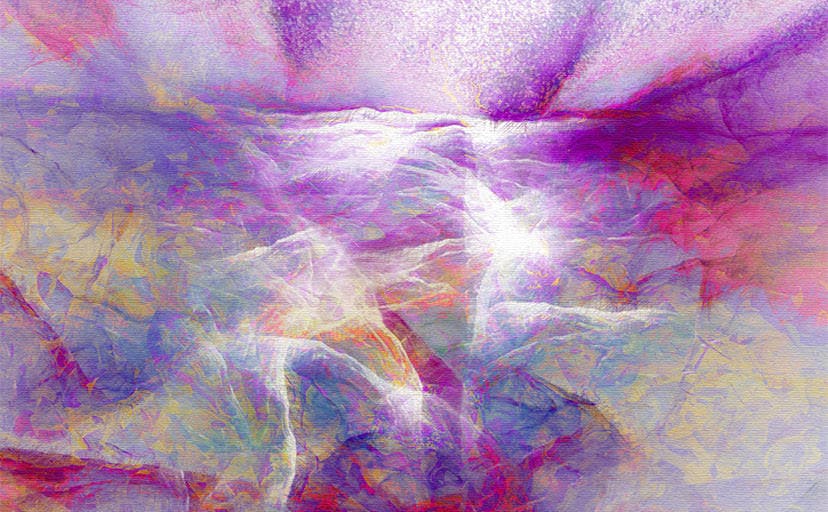
俺が初めてオオカミ様のお社を修繕してから永い時が経過した。
時代も、世情も変わり、年号も変わった。
日本も、日本人も変わったと言われる。
しかし俺を取り巻く世界はそれほど大きく変わってはいない。
昔からの気持ちの良い仲間。家族。
そして見守ってくださる神仏。
俺の生活は、仕事を中心に穏やかに過ぎて行った。
※
一度、縁を得て所帯を持ちかけたが、諸事情により断念した。
しかし、その時にも心の中にはあの方が居り、乱れる事は無かった。
いや、だからこそ断念したのかもしれない。
今だから、そう思えるだけなのかもしれないが…。
※
俺は隠居した親方の後を継ぎ、宮大工の棟梁となる事が出来た。
様々な神仏、様々な神職・住職の方々、様々な弟子達と出逢い、別れてきた。
そして、今も天職として毎日を忙しく過ごしている。
俺が独り身なのを心配して、様々な方から縁談を持ち込んでいただいたが、仕事の多忙さを理由にして断り続けてきた。
自分でも寂しいと思うことは多かったが、自分は神仏に殉じれば良いと独身を通した。
あの時までは。
※
親方が隠居を決めた年の翌正月、親族や縁者を集めて引退の宴が開かれた。
と言っても、親方がお世話になった人へ感謝の気持ちを込めてお礼の為に行うもので、親方が祝ってもらうという趣旨ではない。
いかにも親方らしいと俺も皆も思い、俺たちは全力で手伝いをした。
おかみさんの実家の伊勢からもご両親が見え、非常に大きな宴となった。
宴会中は招いた方全てに宴会場である旅館の部屋へ泊まっていただくのだが、親しい親族や遠方から来られる方の中には、宴会期間外に数日滞在する方も居る。
その為、年明け前にそう言った方の為の部屋をおかみさんと一緒に手配していた時の事。
※
おかみさんの実家から来られるご両親と一緒の部屋に泊まる予定になっている家族が居る。
どこかで見たようなその『榊』と言う苗字に、俺が首を傾げているとおかみさんが教えてくれた。
「○○、その榊さんご家族を覚えているかい?」
家族構成は父、母、そして娘。住所は名古屋だ。
「…どこかで聞き覚えのある苗字なんですが…?」
「ほら、かなり前だけどお前に懐いていて、白血病で亡くなった娘さんが居たろ?」
「ああ!確かに!引越し先は名古屋でしたね!思い出した思い出した!」
あの娘が亡くなった翌年、ご両親は転勤によりこの地を去ったのだ。
「そうか…あの後また娘さんが生まれたんですね。良かったなあ…。でも、なんでおかみさんのご両親と一緒の部屋に泊まられるんですか?」
「ん、色々あってねぇ。おまえ、お伊勢さんに旅行行った時の事覚えてるかい?」
そう、オオカミ様のお社が地滑った年末の事だ。
あの時、おかみさんは久しぶりに実家へと顔を出し、ご両親と仲直りをした。
そして、実家の前に捨てられていた女の子の処遇を手伝う為に二ヶ月くらい実家へ残ったのだ。
「あの時、実家じゃあ乳飲み子の面倒は見られないし、警察からは連絡ないし、いっそウチで引き取っちまおうかと親方に相談しようと思ってたんだよ。
そしたら偶然、お伊勢参りに来た榊さんご夫妻とバッタリ逢っちまって、榊さんご夫妻がこれもなにかの縁だ、って言ってその女の子を引き取る事にしたんさ。おまえにも話した筈だけどねぇ」
…確かに、思い出した。
しかしあの頃の俺の頭はオオカミ様で占められていて、すっかり忘れていたのだ。
しかし、数日とはいえ可愛らしい乳飲み子の面倒を見ていたおかみさんのご両親は情が移ってしまい、それからはちょくちょく榊さんと行き来するようになり、その娘にとっては祖父母同然だと言う。
「なるほど、それで同じ部屋ですか。納得しました」
「うん、だから大きめな部屋を用意してあげておくれね」
※
そして宴の為の手配は全て終わり、年が明けた。
俺は例によって除夜の鐘を聞きながらオオカミ様のお社へと向かった。
最近は忙しさに感けて半年に一遍ほどしか参っていない。
あの少年にも、最後に逢ったのはもう何年も前になる。
俺も歳を取ったなあと思いつつ舗装路となったお社への道を走り、階段前の駐車スペースに辿り着いた。
珍しく先客が居るようで、車が一台停まっている。
中には中年の男女が乗っているようだ。もう参ったのか、これからなのか。
俺は階段を上り、鳥居へと辿り着いた。
松明の明かりの中、お社の前に誰かがこちらに背を向けて立っていた。
ひゅう、と風が鳴り、粉雪が舞い散る。
松明に照らされて立っているその後姿には、長い黒髪が揺れている。
俺の心臓がドクンと波打つ。
早まる鼓動に促されるように俺は歩き出した。
すると俺に気付いたのかこちらを振り向いた。
涼しげな瞳、端正な顔立ち、長く艶やかな黒髪。
そして、松明の炎を写して鈍く輝く銀の髪飾り。
俺の記憶の中にある、あの懐かしい、愛しい姿が其処にあった。
「オオカミ…さま…?」
俺は、呆然と呟いた。
「オオカミ…さま…?」
俺が呟いた瞬間、彼女はビクッと身体を震わせた。
一瞬の後、彼女の瞳から涙が溢れた。
「○○…さま…?」
彼女の口から俺の名が紡ぎ出される。
記憶の中の、あの澄んだ鈴の音のような声で。
舞い散る雪の中、どれほどの時間が経ったろう。
彼女が困惑したように口を開いた。
「あれ…? 私、何で泣いてるの…? あれ…? ○○様って…あれ…?」
俺も混乱していた。
目の前に立つ少女は、紛れもなくオオカミ様だ。
顔立ち、黒髪、声音、そして銀の髪飾り。
何よりも、俺の名前を呼んだではないか。
「貴女は…」
俺が口を開き掛けた時、突然階段の方から声が掛かった。
「沙織、どうしたんだ? 大丈夫か?」
どうやら、停まっていた車から男性が出て来たようだ。
「あ。お父さん!大丈夫。今行きます!」
彼女は涙を拭くと、俺の横を会釈しながら小走りに駆け去って行った。
車のドアが閉まる音が聞こえ、エンジン音が遠ざかって行く。
俺は呆然と立ち尽くす他なかった。
※
突然聞こえてきた笛の音で我に返る。
お社を振り返ると、見事な月明かりの中お社の屋根に誰かが座って笛を吹いている。
月明かりが逆光になりシルエットしか見えないが、直感的にあの少年だと感じた。
美しく響く笛の音を暫く聴いていると、ふと演奏が止まった。
「時、来たれり」
朗々とした声が響く。
もう一度見上げると、既にその影は消えていた。
俺はお社に酒を納め、願いを掛けた。
そして踵を返すと鳥居を潜り、階段を降り始めた。
※
結局そのまま眠れずにいたので、少し早いが午前六時頃に親方の家へ向かう。
集合時間は七時なので、誰か弟子が来ている筈だ。
案の定、俺が付く頃には弟子達が半分は集まっていた。
親方とおかみさんに新年の挨拶をし、鏡割りした樽から酒を酌む。
庭で焚いた火に当たりながら酒をチビチビやっているとおかみさんが声を掛けてきた。
「○○、なんだか心此処にあらずって感じだね。なんかあったのかい?」
「いえ、なんでもないです。もう少しでバスが迎えに来るから支度しないとですね」
言ってる傍から迎えのバスが到着した。
自分の車から荷物を下ろし、親方の荷物や祝いの品等をトランクに乗せてから乗車。
ものの十分でバスは会場の温泉旅館へと到着した。
※
荷物を下ろし、宴会場の状態を確認する。
親方とおかみさんには、先に部屋に行って寛いでもらった。
殆どの支度は旅館側でやってくれているし、今日の宴会は午後三時からなので取り敢えず温泉に浸かって汗を流した。
こんな大規模な宴はなかなか無いので弟弟子達もはしゃいでいる。
しかし俺はオオカミ様の事が気に掛かってはしゃぐ気にはなれなかった。
※
温泉から出て、与えられた部屋に入る。
弟子達は十畳ほどの部屋四つに分かれて宿泊だが、俺は一応個室を頂いた。
とんでもないと辞したのだが、おかみさんが「あんたは特別だよ」と取ってくれたのだ。
茶を入れ、饅頭を食べながらこれからの段取りを思案しているとノックする音が聞こえる。
「どうぞ」と答えると、弟弟子の一人が入って来た。
彼はかつてお稲荷様の一件で取り憑かれて昏倒した男だ。
今では腕を上げ、俺の片腕となっている。
また、数奇な縁で例のお稲荷様の神主さん宅へ入り婿した。
「兄さん、ちょっといいですか?」
「ああ、どうした? まだ昼飯にゃ早いだろ?」
「いえ、それが…」
先ほど、温泉から出て旅館の中を歩いていると見覚えのある女性とすれ違ったと言う。
その後ずっと誰だったか考えていたのだが、ようやく思い出したと。
「俺がお狐様に取り憑かれた時、意識が戻る前に見た夢でお狐様を踏んづけてた巫女さんそっくりなんです」
「ってことは…」
「そう、オオカミ様です。あの方にそっくりな女性とすれ違ったんです!」
「時、来たれり」
少年の声が俺の脳裏に蘇る。
「これは…」
その時が、奇跡の時が来たのか?
どうすればいい? 探しに行くか?
…いや、焦るまい。
もう、これは運命なのだ、と感じた。
※
宴が始まる少し前、俺は会場の最終チェックをする為に部屋を出た。
旅館の方に任せておけば良いとは思えど、仕事柄最終的な確認は自分の目でしないと気が済まないのだ。自分の貧乏性に苦笑しながら会場に向かう途中、
「○○さん…?」
と背後から女性に呼び止められた。
振り向くと、上品な中年女性が立っている。
どこかで逢った事がある。俺の記憶が囁くが、名前と素性は出て来ない。
俺が途惑っていると、女性が微笑しながら話し出した。
「何年振りでしょう…私もすっかりおばあさんになっちゃったから分かりませんよね。ご無沙汰しております。詩織の母です」
瞬間、あどけない少女の笑顔が閃く。
白血病に冒されながら、精一杯生き、微笑みながら逝ったあの少女。
「これは!こちらこそ、ご無沙汰しております。お元気そうで何よりです」
溢れるように戻って来る記憶。
懐かしさと哀しさに、ちくっと胸が少し痛んだ。
「○○さんは本当に変わられませんね。あの頃のまま…」
「いえ、自分もすっかり歳を取りました。もうすっかり中年ですよ。おかみさんから色々と伺っておりますが、今はお幸せなんですね」
「ええ、あの時の○○さんのお心遣いは忘れません。詩織が微笑みながら逝けたのもみな貴方と、…そしてオオカミ様のお陰ですから…」
暫く、二人は黙った。俺は、そして恐らく女性も少女の事を想い出していた筈だ。
少しの後、女性が口を開いた。
「あ、何かご用事だったんでしょう。呼び止めてしまって申し訳ありません」
「とんでもない。また、後ほど旦那様もご一緒にゆっくりお話させて下さい」
俺は一礼して踵を返し、宴会場へと向かった。
※
宴会場はきっちりと設えられており、いつでも宴が始められる状態だ。
親方夫妻は既に玄関で弟子達数人とお客様を出迎えている。
俺が女将さんと少々打ち合わせをしていると、例のお稲荷様の神主さんご家族が現れた。
「やあ、○○さん!この度はお招きいただいて…」
神主さんが上機嫌で喋りだした。
どうも、既に少々飲っているようだ。
「ご無沙汰してます。お元気そうですね」
俺の横に優子さん(娘さん)が来た。
「ウチの宿六がご迷惑をお掛けしてませんか?」
「まあ、少しは」
顔を合わせてぷっと噴出す。
今では、すっかり兄妹の様になる事が出来た。
「何か手伝う事、ありませんか?」
「じゃあ、玄関でご亭主と一緒に受付をお願いします」
料理、飲み物、座布団…しっかり設えられているが、結局もう一度確認する。
確かに手抜かり無い、と納得して時計を見るともう三時直前だ。
そろそろ、宴席が埋まりだしている。俺は親方を呼ぶ為に宴会場を後にした。
※
俺はまだ到着していないお客様を迎える為、親方夫妻と交代して玄関に立つ。
本来なら親方が立つのが道理だが、宴が始まるので一番弟子の俺が代理としてお迎えするのだ。
玄関脇に立ち、まだ到着してない方を名簿でチェックしていると弟子の一人が呼びに来た。
だが、まだ数人来られてない方が居るから、と弟子を帰す。
女将さんが用意してくれた茶を啜っていると、今度は優子さんが現れた。
「始まったばかりなのに抜けてきちゃダメですよ」
「いえ、ウチの人からの伝言です。オオカミ様が宴会に来てるって…。
私のところに飛んできて、俺は手が離せないからとにかく兄さんに伝言してくれって」
「…そう、ですか」
俺は玄関を出て、空を見上げた。
いつの間にか、雪が降りて来始めていた。
「早く来てくださいね」
優子さんは会場へと戻って行った。
※
開始から既に数十分は経過している。
そろそろ出迎えを宿の方に任せて宴席に行っても失礼にはならないだろうと思う。
しかし、なぜか宴席に行けない。
なぜだ? そう、俺は怖いのだ。
恐らく宴席に来ている「オオカミ様」は晦日にお社で会った、あの少女だろう。
彼女はオオカミ様に間違いない。俺は既に確信を持っている。
しかしあの時、彼女は俺のことを覚えていなかった。
どのような形でオオカミ様が現世に顕在したのかは想像も出来ないが、俺の事を覚えていないという事が衝撃だった。
オオカミ様が俺の事を覚えていないという事実。
この状況を冷静に分析すれば、彼女にとって俺は見知らぬ中年男性でしかない。
この宴席で出逢えたという事は、縁が全く無い訳ではないだろうが、現実的にこれからの状況を考えると目の前が真っ暗になってくる。
こんな事ならば、あの頃のまま、精神で触れ合えたままでいた方が良かったのではないか?
生まれてからこんなに不安に、絶望に苛まれた事は無いほど俺は憔悴し切っていた。
「○○、様…?」
オオカミ様の声が聞こえる。どうやら、憔悴の余り幻聴まで聞こえてきたようだ。
「あの、○○様…?」
…幻聴、では無い!ばっと振り返ると、そこにはオオカミ様の姿があった。
「きゃっ!?」
凄い勢いで振り返った俺に驚いたようで、びくっと身をかわす彼女。
そこには、晦日の夜に出逢った、そして俺の記憶の中に住み続けている姿がはっきりと容を取っていた。
「貴女は…」
俺が呟く。
「あ、はじめまして、ですよね。でも、大晦日にオオカミ様のお社でお逢いしましたね。私は、榊沙織と申します」
深々と頭を下げる彼女。艶やかな黒髪がさらっと流れる。
初めて逢った、あの時の様に。
「昔、○○様に可愛がって頂いた姉、詩織の妹です。と言っても私は養女ですし、詩織姉様とは現世では逢えなかったけれど」
彼女は滔々と語りだした。
伊勢で捨てられていた事から、現在に至るまでの事を。
「でも、私は捨てられたことに感謝してるんです。そのおかげで、父様や母様の子になれ、お祖父様やお祖母様にも逢えました。それに、詩織姉様にも…○○様、どうなさったんですか?」
彼女が心配そうに俺の顔を覗き込む。
俺はいつの間にか、涙を流していた。嬉しさによって。
「いえ、何でもありません。貴女が幸せな人生を歩んできたのが感じられて、嬉しかったんです」
俺の答えに彼女はちょっと驚き、頬を染めながらはにかんだように俯いた。
「…お社でお逢いした時、何故かすぐに○○様、って判ったんです。
貴方の事は、父様や母様、詩織姉様から聞いていたからかも知れませんが、それだけじゃなく、…何ていうのかな、パッと閃いたんです貴方が、○○様だって」
そこで俺は気付いた。詩織姉様から聞いた、とは…?
「あ、ごめんなさい。変ですよね…でも、私、良く詩織姉様の夢を見るんです。何か悩んだり、困ったりすると詩織姉様が夢に出てきて助けてくれるんです。
○○様の事もいつも聞いてました。詩織姉様は○○様のお嫁さんにしてもらうんだって言ってました。
でも、沙織ちゃんになら○○様を譲っても良いよって言うんです…」
ここまで言い、彼女はハッとした様に顔を真っ赤に染めて
「ご、ごめんなさい!変な事を言って!
あ、そう言えば私、○○様をお呼びするように言われてたんです。親方のおじ様が早く来い、って仰ってました。さ、行きましょう!」
彼女は俺の手を取ると、会場へと歩き出した。
その手は華奢で、心地良く冷たかった。
※
会場は相当な盛り上がりだった。
沙織と会場に入った俺は直ぐに親方に呼ばれ、暫くは親方とお客様の相手をする事になった。
そのうち榊さん夫妻も近くに来て、想い出話になって行った。
沙織はちょっと離れたところで若い弟子達と談笑していたが、榊さんに呼ばれてこちらにやって来た。
想い出話が続く内、俺は沙織がしている髪飾りについて尋ねてみた。
「沙織は銀の髪飾りを二つ持っているのです」
榊さんの奥様が答える。
「一つはおかみさんの実家の玄関に沙織が置かれていた時、最初から握り締めていました。
もう一つは三歳の時にお伊勢さんにお参りに行った際、奥の宮で不思議な少年が沙織にくれたのです」
その少年は神官服を着た玲瓏な美少年で、沙織に近付いて握らせてくれたと。
ご両親も全く不審には感じず、有り難く受け取ったと言う。
「今着けているのは、三歳の時にもらったものです」
沙織は髪飾りを外すと、俺に渡してくれた。
それは、間違いなく俺があの時、あの少年に預けたものだった。
「この髪飾りをくれた少年は、どんな感じでしたか?」
俺は髪飾りを沙織に返しながら聞いてみた。
「私は小さかったので良く覚えて無いんですが、何故かとても懐かしい感じがしました。まるで…」
言い淀んだ沙織の跡を継ぎ、母上様が話し出した。
「まるで、沙織の血縁者の様でした。顔立ちや雰囲気も似ていて、後になってもしかしたら沙織の本当の兄では、と主人と話したものです。
しかし、とても神々しく優しげな少年でしたので、あの少年は神様の遣いで、沙織は神様が詩織を転生させてくれたのだとその時は考えました」
再び、沙織が話し出す。
「でも、私は詩織姉様の生まれ変わりではなく、妹でした。
○○様には先ほどお話しましたが、私の夢には詩織姉様が良く出てきてくれて、私をとても可愛がってくれました。いつの間にか私の方が姉様よりもずっと年上になってしまったけれど」
親方も詩織の事を想い出したのか、涙ぐんでいる。
詩織の事を覚えている弟子たちも集まってきて、しんみりとした空気に包まれていた。
「最初に握り締めていた髪飾りは、今、持っていますか?」
少しの間静まっていた空気を破り、俺は沙織に聞いてみた。
「はい、ここにあります。随分と古いものみたいで傷が多かったので、ペンダントにしたんです。
沙織は白い胸元からペンダントとなった髪飾りをを取り出し、俺に渡してくれた。
沙織の体温が残り仄かに暖かいそれを受け取った時、心臓がドクンと脈打った。
撫ぜ廻して出来たような擦れ痕と細かい傷が数多く残るそれは、かつて俺が二度目に納め、そして土砂に埋もれてしまったあの髪飾りだった。
「…その髪飾り、どこかで見た事が…?」
いつの間にか俺の後ろに廻り込んで覗いていたお客様が呟いた。
驚いて振り向くと、そこにはオオカミ様のお社を管理している神主さんが居た。
「あ!これは!○○さんがオオカミ様に納めたものじゃないですか!」
その場に居た皆の視線が髪飾りと俺に集中する。
「…○○、本当なのか…?」
親方が搾り出すように問いかけて来た。
「…はい、確かに俺がかつてオオカミ様に納めたものです。間違い、ありません…」
「…え? え? どういうこと、なんですか…?」
沙織が混乱しつつ聞いてきた。いや、周りの全ての人々が混乱している。
俺と、優子さんとその夫、晃を除いて。
「…沙織さんが、オオカミ様だという事ですよ」
晃がボソッと答える。
「晃!」
俺が叱責するが、晃は構わず語りだした。
「兄さんはオオカミ様を愛し、オオカミ様も兄さんを愛した。
二人の余りの愛の深さに、天照大神様が心動かされ、オオカミ様はヒトへ、沙織さんへと転生なさったんでしょう。
ただ、時間を越えることまでは出来なかった。
だから…」
「やめろ、晃」
親方が静かに諌めると、流石に晃はそれ以上口を開けなかった。
宴の席は、いつの間にか静まり返っていた。
※
「さ、お祝いの席が静まっちまったら仕方ないよ!」
パンパンと手を叩きながらおかみさんが声を上げた。
「そうそう、皆さん、さあ飲んで飲んで!」
優子さんも声を張り上げる。
堰を切ったように止まっていた時間が動き出した。
俺も晃にコップを持たせ、ビールを並々と注ぎ込んだ。
俺には沙織がビールを注いでくれ、晃と俺は一気に喉の奥へと流し込んだ。
宴は深夜まで続き、沙織とご両親、若い弟子達は十二時前に部屋へと引き上げた。
※
お客様が全て部屋に戻り、それを見届けてから親方夫妻も引き上げ、最後に残ったのは俺、そして晃と優子さんだった。
三人ともかなり酔ってはいるが、何とか理性は繋ぎ止めている。
優子さんのお酌で静かに日本酒を飲んでいる内、晃が口を開いた。
「…兄さん、沙織さんはオオカミ様ですよね」
「…ああ、多分、な」
「兄さん、どうするんですか?」
俺は、オオカミ様、いや沙織に自分の気持ちを伝える積りは無い事を話した。
「何故ですか!」
晃が声を上げる。
俺は歳が離れ過ぎている事、俺の事を覚えてない事を主な理由として、そうなると常識的に難しいだろうからと答えた。
「意気地無し」
それまで黙っていた優子さんが俯いたままぼそっと呟いた。
「怖いんでしょう。あの方に拒否されるのが」
ぞくっと背筋に寒いモノが走る。
違う。いつもの優子さんじゃ無い…?
「優子…?」
晃も何かを感じたらしい。
優子さんがすーっと顔を上げる。その顔は優子さんのモノではなかった。
目尻はきゅっと吊上がり、高い鼻梁の下には厚めな紅い唇。
そして、微かに紅く光る瞳。この、刃物のように尖った美貌は…
「お狐様…」
晃が息を呑む。
俺の背中にも冷たい汗が流れた。
お狐様の突然の発現に息を呑む俺達。
優子さんがお狐様に憑かれたのは何年振りだろうか。
もう、十年以上前になるのだな、等と脈打つ心臓とは裏腹に思考は妙に冷静に過去を想い出していた。
「お久しぶり、ね。○○さん…そして、あなた(晃)も…」
口の端を上げ、微笑う彼女。
ぞくりとするほど妖艶なのだが、同時に冷たい戦慄を覚える。
俺は、頭を振りながら精神を統一し、大きく息を吐いた。
「なぜ、出てこられたのですか?」
俺が尋ねると同時に、晃がビクッと震える。
「ご挨拶ね。久しぶりに逢えたのに。あの方に対しては弱気なのに、私には随分とキツく当たるのね」
甦る、苦く切なく、そして少しだけ甘い記憶。
お狐様に憑かれた優子さんを晃が抱きしめて鎮めた夜。
あれ以来、彼女が現れる事は無かったのだが…
「なぜ出てきたのかは解っているでしょう? あの時の私の言葉、忘れていない筈よね。貴方達なら」
…確かに、覚えている。彼女は言った。
俺の心が変わった時、また逢いに来ると。
「覚えています。だけど俺の心は変わっちゃいない。俺はオオカミ様だけを愛し続けている」
彼女の微笑が、嘲笑う様に変わった。
「そう。その答えがあの方を見守っていくって事なの?自分の気持ちを伝える事無く」
ふん、とせせら笑う。
「触れてはいけない時には抱きしめたくせに触れられるようになったら諦めるなんて、貴方と結ばれるために御身をヒトにまで落としたあの方が報われないわね」
その言葉に俺は驚愕した。
俺と、結ばれる為に…。
その時、がた、と物音が聞こえた。
俺と晃はビクッと驚き、物音のした方を見る。
そこには、沙織が見覚えのある少女と手を繋いで立っていた。
記憶の中から愛らしい姿が甦り、その少女と重なった。あれは、詩織…
「詩織ちゃん…」
俺が呟く。
詩織は俺の記憶の中にあるままの天使のような微笑を見せ、すっと消えてしまった。
「優子!」
晃が叫んだ。
驚いて振り返ると、倒れ込んだ優子さんを晃が抱き留めたところだった。
その顔はお狐様のものではなく、既に優しげな優子さんのものに戻っている。
呆然と立ちすくむ沙織。消えてしまった詩織。
倒れ込んだまま意識の無い優子さん。
あまりの急な展開に俺と晃は混乱した。
俺は深呼吸をして、優先順位を確認する。まずは優子さんの状態だ。
「晃、優子さんはどうなっている!?」
取り敢えず正常に息をし、脈も大丈夫。心臓も動いている。
ほっと胸を撫で下ろしたが、万が一という事もある。
「沙織さん、救急車をお願いします」
俺が沙織に向かって声を掛けると、晃が答えた。
「いえ、大丈夫です。折角の宴の初日にそんな縁起の悪い事は出来ません。俺が自分で病院に運びます」
「馬鹿野郎!お前も酒飲んでるだろうが!そんな事言ってる場合か!」
晃を睨み付ける俺の横を沙織が通り過ぎ、優子さんを抱く晃の前に座り込んだ。
沙織は晃から優子さんを抱き受けると、自分の白い額を優子さんの額に当てた。
数分の後、沙織が顔を上げる。
「大丈夫です。彼女はもう奥様の中には居りません」
呆気に取られる俺と晃。
「お部屋で横にさせて上げた方が宜しいでしょう。○○様、お手伝いしてあげて下さい」
しかし晃は一人で優子さんを抱き上げ部屋に帰って行き、広間には俺と沙織が残された。
※
「○○様、少し散歩しませんか?」
沙織が俺を見つめながら聞いてくる。
そして数分後、俺と沙織は旅館の庭にある池の辺をゆっくりと歩いていた。
空を見上げると見事な月が光っている。
沙織の歩みが止まる気配を感じ、俺は月明かりに照らされて白く浮かぶ沙織に目を向けた。
「…宴会から部屋に戻ってうとうとしていたら、久しぶりに姉様の夢を見たんです」
そして、夢から覚めると詩織がそのまま存在していたのだという。
詩織は微笑みながら沙織の手を取って俺達の居た宴会場へと導いた。
そして、お狐様が優子さんに憑いている所に出会したと。
「彼女の言葉を驚きながら聞いていたら、姉様が私をとん、と押したんです。そうしたら、私の中に、爆発したように、全てが、戻って…」
沙織は漆黒の瞳から、宝石の様に輝く涙を溢れさせた。
「貴方と、初めて、逢った時の事、貴方に、抱き締められた時の事…」
もう言葉になっていない。俺の両目からも、驚くほどの涙が溢れてきていた。
両手を顔に当て、泣き笑いのような表情をしている沙織。
俺は両手を広げ、辛うじて声を絞り出した。
「お還りなさい」
沙織は俺の腕の中に飛び込んで来た。
そして、はっきりと応えた。
「ただいま、還りました」
抱き締めたその華奢な肉体は、あの時と同じ様に熱かった。
どこからか微かに流れてくる笛の音を感じながら、月明かりに照らされた二人の影は重なったままだった。